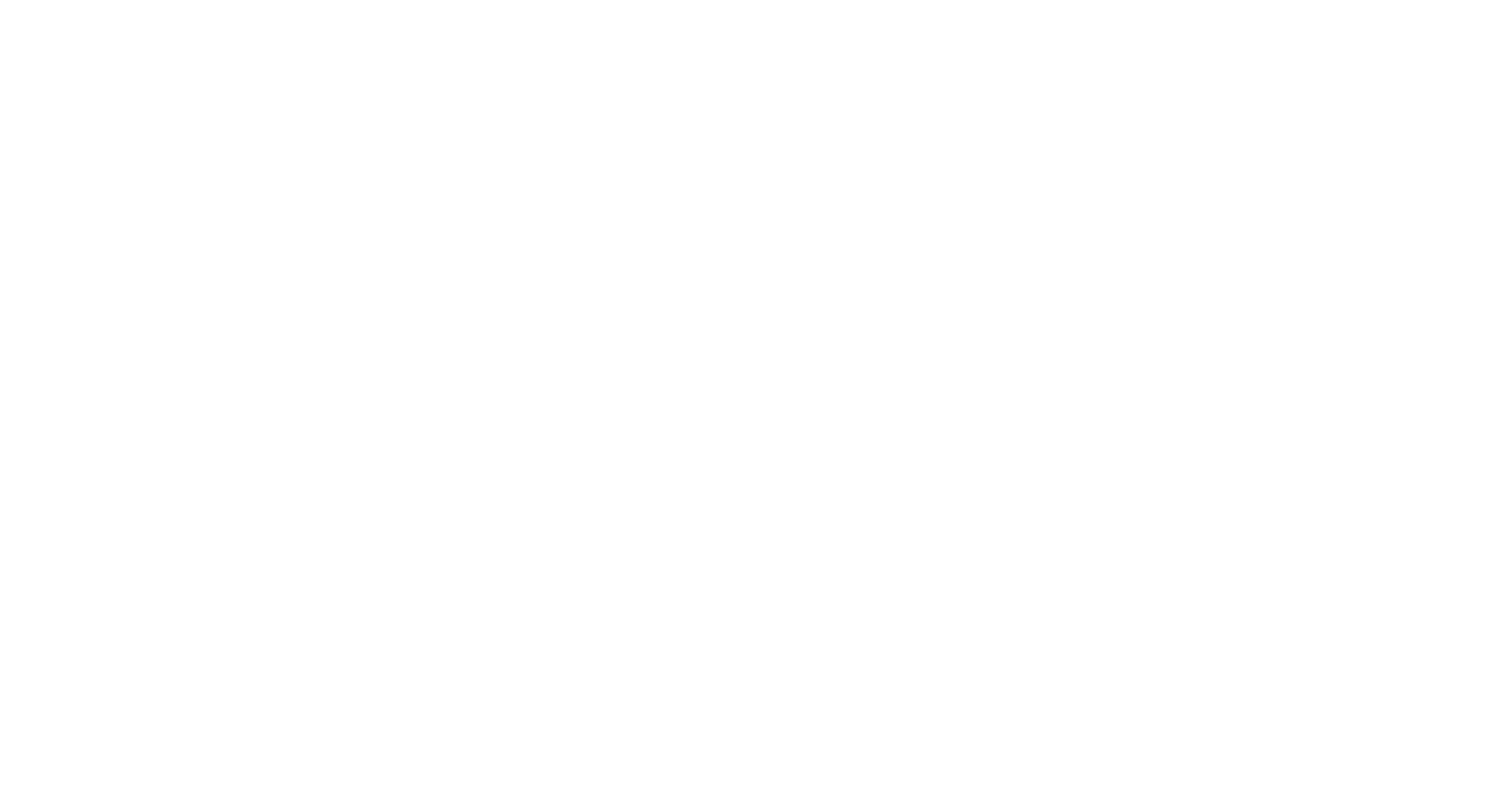バンライフを自作ハイエースで1年間、実践したYaiYu(@yusukeyaida)こと、矢井田裕左です。
近年、若者を中心に急増している車で移動しながら旅するように暮らすライフスタイル「バンライフ」。

また、完全なオフグリッド(自給自足)とは言えないものの「セミオフグリッド生活」に近く、移動できる観点から「災害に強い」生活としても注目されています。
そして私は、2019年から2020年にかけて「完全バンライフ」、つまり家を引き払って車に移住した実践者であります。

この記事はそんなバンライフについて、実体験を踏まえたかなり濃密な内容でお届けしています。
バンライフ(VANLIFE)とは?
バンライフって何と聞かれた時、あなたはどう答えますか?

「車中泊」と同じなのでは?
そう思う方がほとんどだと思います。
でも車中泊って色々あると思いませんか?
- 土日の休みを使った1泊2日の車中泊
- GWなどを使った5泊6日の車中泊旅
- 数ヶ月、北海道を一周まわる車中泊旅
しかし、規模感は全然違うのに、全て車中泊と呼びますよね。
だとするとバンライフは上記のどれに当てはまるのでしょうか?
それを判断するには、
- バンライフの定義
- 先駆者フォスター・ハンティントン
- #vanlife
を知る必要があります。
バンライフの定義
バンライフの定義は以下の通り。

「家を持たず」「都会暮らしではなく」「田舎暮らしでもない」。本当に必要なモノだけを持って、クルマに積み、行先は決めず旅にでる。それがバンライフ。
車という限られたスペースの中に生活のすべての「モノ」を載せ、本当に必要なモノだけで生活する「ミニマル」なライフスタイル。
様々な場所に移動しながら、オフグリッドな生活の中で、自然やアウトドアを満喫しながら、仕事やプライベートを充実させることができるのがバンライフ。
フォスター・ハンティントン
その定義を造ったのは、世界で初めてバンライフを行い「vanlife」という言葉の生みの親、アメリカ人の「フォスター・ハンティントン」。

そんな先駆者フォスター・ハンティントンは元々「ラルフローレン」のコンセプトデザイナーや出版社「ハーパーコリンズ」で働いていたエリートです。

毎日の忙しい日々に嫌気がさして、家を捨て生活に必要な最小限のモノをバンに詰め込みバンライフが始まりました。

彼の場合は朝起きたらサーフィン、冬はスノボー、日中はスケボーと、自分の好きなことはとことんやりつつも、

しっかりと「リモートワーク」で生計を立てていたそうです。
彼がクラウドファンディングで作った写真集は、日本でも2020年に日本語版として販売され、今や「バンライファー(バンライフをしている人)」の間では「聖書」に近いほどの存在となっている。
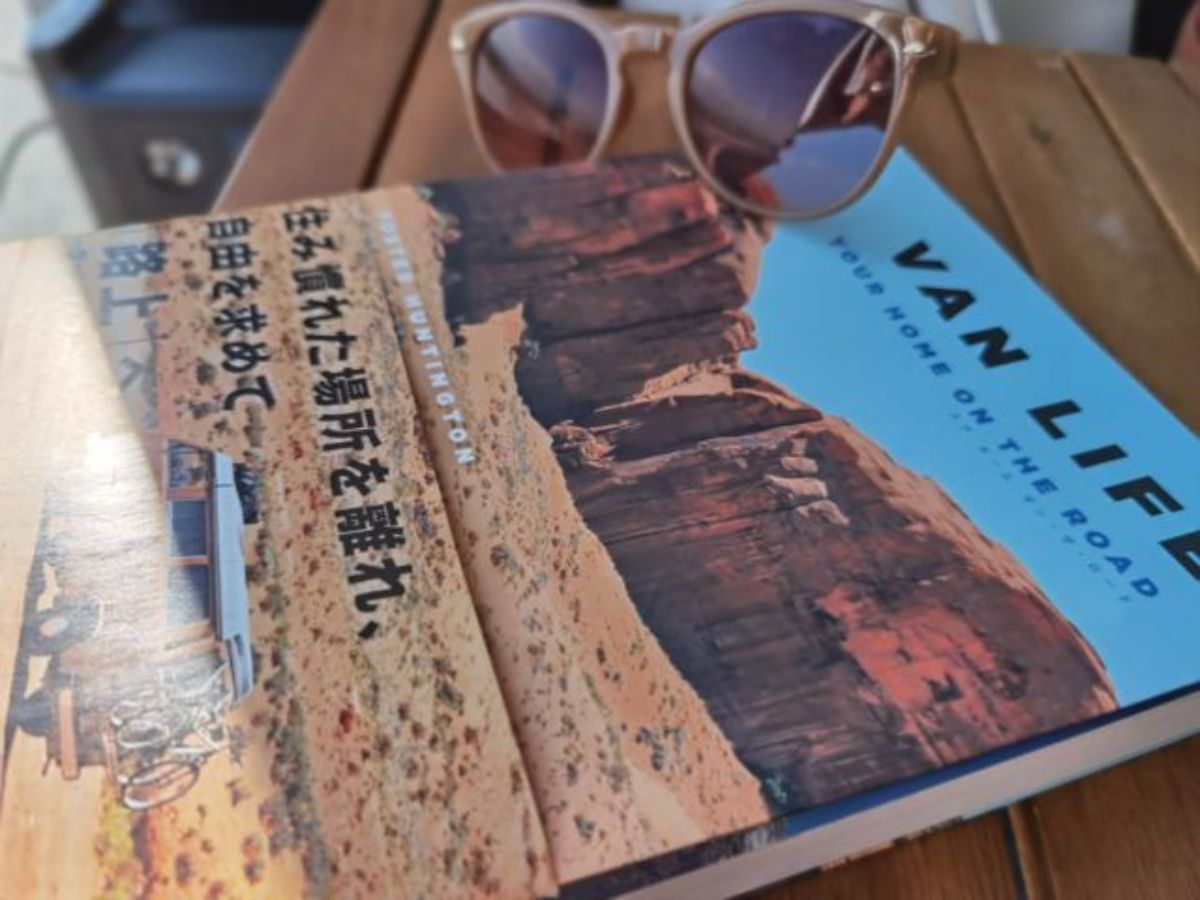
 YaiYu
YaiYu私も持っております!
#vanlife
彼がインスタグラムで「#」で投稿した「#vanlife」によって、世界中でバンライフのコミニティが形成され、最低限のモノで最高の豊かさを求める発信が広がっていきました。


私がバンライフを始めた2019年の段階では「#vanlife」の投稿数は「400万件」ぐらいでした。
フォスター・ハンティントンがバンライフを開始したのが2011年と言われているので、8年間で400万もの#が使用されたことになる。
しかしながら、そんなのは序の口で、2023年の段階ではすでに「1500万」#が使用されているので、この現代において世界中で広がりを見せているのは確かです。
ちなみに「#バンライフ」は30万ぐらいなので、日本ではまだまだこれからどんどん伸びていくと予想されます。
そんなフォスターがどんな人生を過ごし、どんな実績を積み上げたのかを詳しく書いた記事もあるので合わせてご覧ください。


結局、バンライフって?
上記を踏まえてバンライフって結局、何だったのでしょうか?


まず定義の1番冒頭に、「家を持たず」と書かれていました。
そう、バンライフは「住んでいる家を出て完全に車で生活するライフスタイル」なのです。
車中泊はあくまでも、バンライフを行う「手段」の一つでしかありません。
フォスターは毎日の忙しい日々に嫌気がさして、バンライフを始めましたが、それもバンライフを始めるきっかけの1つ。
バンライフ実践者の私が考えるに、今の若者を中心にバンライフを始める人が急増しているのは、
- バンライフをすることで今後の人生の飛躍に繋げたい
- 何かに「気づいたから」バンライフを始めた
- 普通に会社員として働くことへの疑問
- テレワーク、リモートワークができるからこそのライフスタイルの手段
- 賃貸や分譲の家に住むことが当たり前なのかの問いかけ
などなど、実に多様化していると思います。
バイアスがかかった今の中高年の方々は、こういった若者の挑戦を温かい目で見守っていただければ幸いです。
バンライフに向いている人・向いていない人
ではバンライフは、どんな方でも実践可能なのでしょうか?
正直、私はあまり「向いている人ではない」と振り返って思います。
そもそも、引きこもり体質で、人と多く話したり、移動するのもそれほど好きではないから。
だったらやるなよという感じですが、クルマの中はプライベート空間なので、うまくバランスが取れたように思います。
では、一体どういった方がバンライフに向いていて、どういった方が向いていないのか。



バンライフを実践し、様々な方に出会ってきた体験から考察してみました!
バンライフに向いている人
まずは向いている人からのご紹介。
- 世俗に紛らわされない人
- 環境に適応できる人
- ミニマルな生活が自然とできる人
- 意思決定能力が高い人
世俗に紛らわされない人
バンライフって、実際のところ誰でもできそうだけれども、ほとんどの人は行動に移せてないんですよね。
だって、親がどうこう、知り合いがどうこう、仕事がどうこうとか結構な人に色々、言われるんです。
そこで怖気付いちゃって行動に移せないパターンが多い。
でも実際、バンライフを実践した方は、他人からの意見や評価に対して、
「あ〜自分はこの生活が自由で向いてそうだから、周りになんと言われようともこのライフスタイル、まずはやってみるわ〜」
ってな軽い感じで決定できる人が向いているのだと考えます。
環境に適応できる人
バンライフは環境の変化の連続です。
- 日々、寝る場所は異なる場合が多い
- 日々、食事をとる環境が変わる
- 日々、買い物する場所は異なる
- 日々、気温、天候に生活が左右される
- 日々、水、電気などのインフラを意識する必要がある
などなど、数え上げればまだまだあると思います。
そういった環境の変化に適応し順応できる人は、バンライフに向いていると言えるでしょう。
ミニマルな生活が自然とできる人
上記のフォスターハンティントンもはそうでしたが、サーフボードやスケボーがあれば、他に何もあまり望まないサガの人でした。
実際、私もモノは多くもたず、今は定住しているにもかかわらず、持っている荷物は今でも全部、車に入るぐらいしか持っていません。
そういったシンプルでミニマルな生活を無理して行うのでなく、自然とできる人はバンライフに向いているでしょう!
意思決定能力が高い人
私的には、この「意思決定能力が高い人」がもっともバンライフの必須条件と思っています。
どういうことかというと、
- 今日はどこで食材を調達しようか
- 今日はどこでご飯を調理しようか
- 今日はどこでご飯を食べようか
- 今日はどこでお風呂に入ろうか
- 今日はどこで車中泊しようか
- 今日はどこで仕事をしようか
などなど、日常ではなんの意思決定が必要でない日常生活すべてが意思決定が必要になってきます。
私はこの意思決定の連続が、まったくの苦痛ではなかったのですが、車中泊で旅をする人から「意思決定の連続がしんどい」と話を聞いたときに、これはなくてはならない能力なのだなと考えさせられました。
向いていない人
ではバンライフに向いていない人はどんな方でしょうか。
- 意思決定能力が低い人
- 快適な生活を求める人
- 移動生活で収入が見込めない人
- 承認欲求が強い人
意思決定能力が低い人
向いている人で解説したので、当然、意思決定能力が低い人は向いてないことになります。
では、意思決定能力が低い人とはどういった方でしょうか?
日常生活に当てはめてみると
- 職場で上司の言われるがままの仕事をこなうほうが好む人
- 職場で意思決定をするような立場になりたくない人
- 自分の人生をしっかりと意識して未来を考えれていない人
などなどでしょうか。
快適な生活を求める人
バンライフは、憧れのライフスタイル、そんな描写の仕方をメディアは伝えていることもあるでしょう。
いやいや、全然違いますから・・・
車の中という狭い環境で、さらに日常生活の全てのモノを収納しているわけですから、住居スペースなんてほんのちょっとしかありません。
雨の音がうるさくて寝れないこともあるし、お風呂に入れないこともあるし、電気が尽きることもしばしば。
もちろん、試行錯誤で快適さは大きく変わると思いますが、どこまでいっても家のように快適になるということはあり得ません。
移動生活で収入を見込めない人
向いていない人のランキング1位は、間違いなく移動生活において収入を見込めない方でしょう。
下記でもバンライファーの仕事事情についてもお伝えはしているのですが、バンライフをこなすには、継続的な収入があることが前提です。
リモートワークやテレワークなど、場所に縛られない働き方ができない人には向いていないというか不可能に近いでしょう。
バンライフに必要なもの
ここからは、私が実際にバンライフを始める前と始めた後、必要なものは何だったかをお伝えしていきます。
流石に、細かい内容になるので全ては書ききれておらず、別記事に詳細を記載しておりますので、興味のある部分は合わせて記事をご覧いただければ幸いです。
クルマ
バンライフを始めるわけですので「クルマ」はなくてはならない相棒です。
私はバンライフを始める際に、車をどれにしようかめちゃくちゃ迷いました。
- 国産車 or 外国車
- 1ナンバー or 3ナンバー or 8ナンバー
- ディーゼル車 or ガソリン車
最低でもこの3つを考慮しつつ考える必要があります。
もちろん600万円以上するような「バンコン」や「キャブコン」のキャンピングカーを購入するんだろという人は、どれを購入するかを探せば良いのですが、私のように、キャンピングカーではなく、市販の車をDIYしてバンライフしたい人にとってはかなり重要になってきます。
ハイエース
結果として私はバンライフの相棒として選んだのが「ハイエース スーパーロングバン」という貨物車の最大サイズのクルマです。


上記の3つの項目で言うと
- 国産車
- 1ナンバー
- ディーゼル車
です。
このクルマを選んだ理由は「3点」あります。
- 燃費がいい
- 車高が「2.2m」
- 運転しやすい
こちら、解説するとかなり長くなってしまいますので、ハイエースについて詳しく書いた記事を合わせてご覧ください!


フォルクスワーゲン
そしてハイエースと購入を悩んだのが、バンライフといえば「ワーゲンバス」。


上記のフォスター・ハンティントンもバンライフを始めたクルマはフォルクスワーゲンの「ヴァナゴン」なのだから、憧れること間違いなしですよね。
しかしながら、調べれば調べるほど、現実的に難しいことが判明しました。
それを詳しく解説している記事がありますので、フォルクスワーゲンでバンライフを始めようと思っている方はご覧ください。


ベンツトランスポーター
皆さんはベンツのトランスポーターをご存知でしょうか?


通称「ベントラ」とも呼ばれるこのクルマは日本でいうトヨタのハイエースのベンツ版と思っていただいて遠くない存在。
正直、このクルマも憧れがあり、購入を検討していましたがこちらも断念。
断念した理由などは、別記事に記載しておりますのでご興味のある方はご覧ください!


軽自動車
近年になり、バンライフを始める層が主に20代、30代になってきた中で、手持ちの少ない予算からか、軽自動車でバンライフを始める若者が増えてきています。
私がバンライフをしていた2019年の当時でも、軽自動車でバンライフをする夫婦がいましたので、全く不可能でもないと思います。
おすすめの車種として、
- SUZUKI「エブリィ」
- DAIHATSU「アトレー(ハイゼット)」
- HONDA「N-VAN」
この3つが挙げられるでしょう。
この3つに共通することは、私がハイエースバンを選んだのと同じく、「バン=貨物車」だから。
貨物車だからこそ、空間を最大限に使用できるだけでなく、壁面をうまく利用できたりと様々な利点があります。
また、バンライフをやめた後でも、比較的「需要が高い」ので高く売却できることも魅力の一つだと考えます。


キャンピングカー
なぜキャンピングカーにしなかったのか?


それは、先駆者フォスターのような暮らしに憧れたからです。
私はバンライフをする前から持たない暮らしがしたいと思っていて、キャンピングカーは便利なのですが、それだとなんか違ったわけです。
何もない貨物車から、自分が必要な最低限の装備とものを持って旅をしたいと思っていたので、選択肢として1番最初に外れたのがキャンピングカーでした。
とはいえ、キャンピングカーを否定するわけではなく、本当はキャンピングカーで旅をすればもっと楽だっただろうなとは思います!
ポータブル電源
バンライフをする上で車の次に必要なモノは、電力を確保するための「ポータブル電源」です。


2019年の当時は、ポータブル電源は今ほど性能の良いのはなく、販売されている数もとても少ないモノでした。
しかしながら、2023年にはかなり高性能で安いポータブル電源が販売されています。
バンライフ中に、ポータブルバッテリーに電気を充電する場所や方法は
- 電源があるキャンプ場
- 電源が使えるカフェ
- ソーラー電池
- 車載充電
などがあり、これらすべてを駆使して電力の安定確保を常に行っていくのがバンライフの試練でもあり、楽しみでもあります。
このメディアでは、様々なポータブル電源をレビューしていますので、是非とも購入の際の参考にしていただければ幸いです。
ポータブル電源大手ブランドと電池容量別の一覧
ソーラーパネル
そしてソーラーパネルも必須級ですね。


クルマの上にDIYするのであれば問題ないですが、私はクルマを外から見た時に、キャンピングカーだと思われたくなかったので、外装部分のDIYは行っていませんでした。
晴れていれば、クルマを停車し、ソーラーパネルを設置してよくどこでもルールの範囲内で太陽光発電したものです。



私はこのソーラーパネルでどれぐらい充電されるのかの実験が楽しくて好きでした。
車中泊グッズ
バンライフを行う上で、様々な車中泊グッズも購入しました。
- 小型扇風機
- 電気毛布
- LEDライト
- 強力磁石
- 断熱材
- ベッド
実際に購入したグッズを別記事で紹介予定なので、しばしお待ちください!
トイレタリー
車中泊に必要なトイレタリー用品の種類は、以下の通りです。
- 歯ブラシ・歯磨き粉
- 石鹸
- シャンプー
- リンス
- タオル
- トイレットペーパー
- 生理用品(女性)
- 日焼け止め
- 虫よけスプレー
- かみそり
- 絆創膏
- 目薬
- 耳かき
- 爪切り
- 歯間ブラシ
- コットン
- 綿棒
- トイレシート
- ペーパータオル
- ゴミ袋
トイレタリー用品を保存する際は、以下の点に注意しましょう。
- 水に濡れない容器に入れる。
- 密閉容器に入れる。
- 日光が当たらない場所に保管する。
車中泊に必要なトイレタリー用品の種類を十分に用意し、適切に保存することで、災害時の車中泊を快適に過ごすことができます。
私の場合は、家にあったクローゼットをクルマにそのまま積み込んでいたので、収納できていました。(下記画像の左下がクローゼット)


バンライフの問題点
バンライフをすることでたくさん得るものが存在します。
- 全国の美味しい食事が食べられる
- 全国の温泉に入ることができる
- 全国のサウナに行くことができる
- 全国に知り合いが増える
- バンライフが終わった後、どこで住むのかを探せる
- 人生においてステップアップできる
などなど。
私は若者にそういったチャンスと経験とそして遊びをしっかりと楽しんでほしい。
しかしながら、バンライフをする上で大事なことは、バンライフにおけるマナーを守ったり、問題点を認識しておくことが大事です。
ここでは、バンライフの様々な問題をピックアップし、1つずつ解説していきます。
道の駅のマナー問題
2019年にバンライフを行っていた時からよく目にしていたのは、「道の駅」のマナー問題。


あくまでも民間になりますが、日本RV協会が提言している「公共駐車場でのマナー厳守10ヵ条」をご紹介します。
【出典】日本RV協会「マナー・ごみ問題-マナー厳守への呼びかけ」公共駐車場でのマナー厳守10ヵ条
- 長期滞在を行わない
- キャンプ行為は行わない
- 許可なく公共の電源を使用しない
- ゴミの不当投棄はしない
- トイレ処理は控える
- グレータンクの排水は行わない
- 発電機の使用には注意を払う
- オフ会の待ち合わせは慎重に
- 車椅子マークの所に駐車しない
- 無駄なアイドリングをしない
この10ヶ条は、下記でも紹介しているのと同時に、道の駅のマナーについては詳しく解説記事を設けていますので車中泊を行う方は必ず頭に入れておきましょう!


暑さ・寒さ問題
バンライフをしていたとき、実は何回か死にかけたことがあります。
それは、夏の日の朝・・・
ありえない量の汗とともに起床した時・・・
忘れもしない2019年の新潟県の夏の日に、フェーン現象で40℃を超えた日があり、その日は海辺の近くの道の駅で就寝していました。
夜は風も吹き、そんなに暑くはなかったのですが、朝方、日差しが出てきた瞬間、気温が爆上がりし、危うく閉ざされたクルマの中で死んで干からびて死んでしまうところでした。
逆に冬の寒い日は、朝起きるとクルマのドアが凍りついて開かない場所でも車中泊したことが、それは、長野県の高ボッチ高原・・・
バンライフをする前に、と車に断熱材をしっかりと仕込んでいたおかげかなんとか乗り切ることができたと今は思っています。


ゴミ問題
ゴミは食事を作るときだけでなく、何事においても発生します。
私がバンライフで出たゴミをどうやって捨てていたのか挙げさせていただきます。
- 買ったところで捨てる(コンビニならコンビニ、スーパーならスーパー)
- キャンプ場
- ゲストハウス
- ガソリンスタンド
- サービスエリア(購入した場合のみ)
- 旅先で出会った方に、有料で捨てさせていただく
- クリーンセンターで有料で引き取ってもらう
私のモットウとして、不法に投棄はゼッタイにしたくありませんでした。
当時はバンライフってだけで、世間から注目も浴びる存在。
だからこそ、マナーをしっかりと守り、バンライフが今後の未来にとって、一つのライフスタイルとして確立するには、世間から認めてもらう必要があります。
そのバンライフをやってる奴がマナー違反だといつまで経っても世間からは厄介者と認定されますので、上記で紹介したマナーとゴミ処理をしっかりと守っていきましょう!



お陰様で助手席にゴミが捨てれず溜まっている時が多々、ありました・・・
トイレ問題
バンライフ中、「トイレ」は下記の場所で行っていました。


- コンビニ
- ショッピングモール
- 様々なお店
- キャンプ場
- 道の駅
- 車中泊スポット
- ガソリンスタンド
ありがたいことに、日本は様々な場所でトイレをすることが可能です。
もちろん公共の場所もありますので、ありがたくさせていただいております!
ただ、バンライフをしているならではのトイレ問題が出てきました!
それは女性ならではの問題かもしれません。
夜中に一人で暗いところを歩いてトイレに行くのは怖い・・
虫だらけのトイレは抵抗がある・・
女性でも「そんなの平気ですよ!大丈夫です!」という方はいるかもしれませんが、私たちは「誰もが憧れるバンライフ」から「誰もが楽しめるバンライフ」を目指して行動しているので「トイレ」について本気で考察してみました!
そこで女性でも安心して「トイレ」をすることができるように、車内に簡単に設置できる「トイレ」についてまとめました!
- ユニセックスポータブル尿ボトル
- ポータブルトイレ
- 折り畳みトイレ
- コンポストトイレ
ポータブルトイレだけとっても、これだけの種類が世の中にあります。
紹介しております様々なトイレは、「バンライフ」だけではなく、災害時の際にも使えます。
避難所にはもちろん、断水時にも対応可能。
さらには、高速道路で渋滞中の時に我慢できなくなった緊急用にも使えます!


お風呂問題
バンライフの醍醐味の1つとして間違いないのは、全国の「温泉」「銭湯」「サウナ」に入れること。
私も様々なスーパー銭湯に行き、温泉やサウナを満喫しました。
しかし、バンライフのお風呂には大きな問題がありました。
それは、間違いなく「コスト」。
例えば平均的なスーパー銭湯であれば、「1回800円以上」。
毎日、入ったとして、1ヶ月で、「800円 × 30日 = 24000円」になります。
もちろん1人の価格がこれだけなので、夫婦やカップルの場合だと、「月5万」



もはや家賃のレベル・・・
なので、私が実際にしたお風呂の探し方と、その価格対策、そして防災にもなるお風呂に入れなかったときの対策グッズを別記事にて今後、ご紹介していきますのでお楽しみに!
食事問題
車中泊の際に車内に用意しておくと便利な調理器具をご紹介します。
- カセットコンロ
- ホットサンドメーカー
- 電気ケトル
- 電気ポット
- 調理器具セット
車内に調理器具を用意しておくことで、災害時の車中泊でも、温かい食事をとることができます。
上記でお伝えしたお風呂代がめちゃめちゃ高いので、できる限り車内で自炊していました。
上記の主に、電気を使用するものは実はほぼ使わないようにしていて(電気が足りなくなるから)、主にガスコンロを使用していました。
その際に、実際にバンライフの中でどうご飯を炊いていたのかを記載している記事もあるので併せてご覧ください。


睡眠問題
バンライフや車中泊を行う際に、皆さんも経験するのがもちろん就寝。
私の場合、クルマが大きかったので、実は、セミダブルベッドのマットレスをそのままぶちこんでいたので、睡眠に関しては寝すぎるほど、寝れていました。
注意したのは以下の通り
- 車中泊スポットの地面に傾斜がないか
- 車中泊スポットの人が集まる場所から距離があるのか
- トイレは近いのか
- 治安は大丈夫か
などなどです。
まずクルマを停めて確認したのが「傾斜」。
車中泊の際に傾斜がると、横になったときに、めちゃめちゃ強く感じるのです。
頭が下になった時とか血が上るんじゃないかとか心配になり夜も寝れないので、傾斜がある道の駅に出会ったら次の道の駅まで移動したぐらい傾斜には気を遣っていました。



中には気にならない人もいるようなのですが、その人はすごいと私は思います。
水問題
バンライフをする上でも、災害時に車中泊をする場合でも、水を十分に用意しておくことが重要です。
車中泊に必要な水の量は、およそ「1日1人あたり1.5〜2リットル」。
飲料用だけでなく、調理や衛生用にも結構、必要でした。
バンライフ中の水の確保方法には、以下のようなものがあります。
- ペットボトルの水を購入する
- イオンモールなどでボトルだけ買って何度も入れれるのを購入する(←これしていました)
全国、どこへ行っても結構、地方だとイオンがたくさんあります。
水を入れ放題なので、かなり重宝したのですが、ここで思ったことは、ハイエースを選んでよかったこと。
全国のイオンモールを転々と移動する中で、駐車場の高さ制限を設けるところが多々ありますよね。


大体それが、「2.3m」なのですが、なぜ2.3mかというと、ハイエーススーパーロングの車高が「2.2m」なのですが、このクルマが入るようにと考えています。
日本でも数多く、この商用車が走っているので、2.2m制限だと、かなりのハイエースやキャラバンが入れなくなっちゃいますよね。



当然ながらキャンピングカーは入ることができず、私はこの理由でキャンピングカーを選ばなかったのもあります。
排水問題
現在、国内のキャンピングカー保有台数は10万台突破し年々増加傾向。


しかし、排水処理できる施設は少なく、道の駅などで捨てるといったマナー違反も増えているので、警告もされている状況は続いています。
では一体、キャンピングカーで長期の車中泊をされている方は、どこで水の廃棄をしているのでしょうか?
主に廃棄する水は下記の2種類です。
- グレイウィーター:中水と呼ばれ、飲料水の上水と、汚水などの下水の間となる、台所や洗濯などの排水
- ブラックウィーター:し尿などの下水
実際に私が「水道局」に電話取材をし回答をもとに結果をお伝えしていきます。
ダンプステーション
まず1つ目の廃棄場所として「ダンプステーション」が挙げられます。
ダンプステーションとは、キャンプ場や道の駅などで設置されている、排水を有料で処理してくれるサ場所のことです。
とはいえ、まだまだ設置が少なく、キャンピングカーユーザーからすると、まったく足りておらず、正直、皆さんどうやって処理しているのか不明・・・
汚水枡
次に「汚水枡」。
マンションなどの敷地内の汚水を、公共下水道本管へ流入するために設けられる桝。
許可をもらうことで、住宅敷地内にある小さなマンホールからキャンピングカーだとホースで接続して汚水を流すことができます。
自宅のトイレ
ほとんどのキャンピングカーユーザーは、この自宅での処理が基本だと思います。
とはいえ、長期で旅をしている人にとっては、わざわざ自宅に帰ることができなかったりと、なかなか日本では汚水を捨てれる場所の普及は進んでいません。



実はキャンピングカーでバンライフするハードルって「排水問題」が私は結構、大きいと思っています。
仕事の問題
私自身、1年間バンライフを行い車中泊ユーザーの友達がたくさんできたので、その人たちがどのような仕事をしているのかをよく知っています。


まずはそのバンライファーの仕事(職業・副業・アルバイト)を一覧にまとめました。
- リゾートバイト
- 短期バイト
- データ入力
- 移動販売
- ブロガー
- アフィリエイター
- Webライター
- Webデザイナー
- Webマーケター
- エンジニア
- 動画配信者(Youtube、Tiktok)
- 動画編集者(切り抜きなど)
他にもありますが、このぐらいにしておきます。
そして上記の仕事に多く共通していることは、
- 固定の場所を必要としない
- テレワーク可能
- ノマドワーク可能
- テレワークとは?
-
「tele = 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語で「出社の負担を減らすことが目的の働き方」の意味を含む。
よく似た意味の言葉でリモートワークがあります。
英語で「remote=遠隔・遠い」、「work=働く」の二つが合わさってできた造語で「遠くで働く」意味の言葉。大きく意味が違うわけではないと認識しているので、本ブログではテレワークに統一します。 - ノマドワーク
-
ノマド(nomad)とは、英語で「遊牧民」を指す言葉。
定住地を持たない遊牧民のように「特定のワークスペースを持たずに移動しながら仕事すること」、すなわち、オフィスに限定せず、様々な場所で働くこと。
コロナウイルスの影響で様々な働き方が注目される中、上記のように「どこでも働くことができるスキル」をもっておくことは、今後の「時代や環境の変化」へ対応することも可能になります。
しかし、上記の仕事の中でも、実際には「おすすめしない仕事」と「おすすめする仕事」があります。
その点を「何故おすすめできないのか?」「何故おすすめなのか?」の理由もしっかりと踏まえて、かなり詳しい記事にしたものがあるので、是非とも収入面で不安の方は合わせてご覧ください!


住居問題
バンライフとは住居を手放してクルマに引っ越しするライフスタイルですが、以下のものは一体どうすればいいのでしょうか?
- 家からクルマに入らなかったモノ
- 住民票
- 選挙
こちらも実体験からお伝えしていきます。
家からクルマに入らなかったモノ
実際、家を出てクルマに移り住むとき、私の場合はそれほど荷物は溢れなかったのですが、クルマのパーツなどを取り外したので、これは自宅の方で預かってもらいました。
また賢い手段として、「サマリーポケット」というサービスをオススメします。
最大の理由が「模様替え」です。
クルマの限られた空間の中で、春夏秋冬の服をすべて入れ込んでいるとかなり嵩張ります。
サマリーポケットは、荷物を有料で預かってもらい、必要になれば送ってくれるサービスです。
- 面倒な契約は一切無し!
- 荷物を箱に詰めて、送るだけ
- 荷物を預ける時も取り出す時もスマホ1つで配送業者を手配、クルマにいながら全部完了
- 急に荷物が必要になっても、1点から最短翌日でお届け
夏の間に着ない服などは、サマリーポケットに送っておき、また必要になったタイミングで送ってもらいましょう!
郵送物
上記のサマリーポケットもそうなのですが、バンライフ中の配送や受け取りはどうすれば良いのでしょうか?
なんとなく配送は最近は、コンビニでも可能なので、郵送物を受け取る方ですが、
- 全国のコンビニ
- 宅配業者
- 郵便局
などで受け取ることができます。
受け取るにはちょっとテクニックが必要で、ちょうど配送物が届きそうな頃合いに、いる場所を予想して指定の場所に配送する必要があります。



慣れてくれば案外、カンタンですよ!
住民票
私たちは、賃貸マンションからハイエースに引っ越したました。
引っ越しすると、市役所での転出届、転入届の手続きが必要になります。
引っ越しから14日以内の異動が義務付けられていて、手続きを怠ると罰則規定もあり、日本で生活するためには、「住所なし」というわけにはいきません。
住民票に「ハイエース」とは記載できませんので、住民票の住所は実家に置かせてもらっています。
そして、住民票のある場所で住民税の支払いをしています。
そして、住民票のある場所で住民税の支払いをしています。
もし実家がないという方は、下記の3つのサービスから選ぶといいと思います。
それぞれが有料のサービスとなり、価格も使い方も違うので、自分の合ったサービスを選ぶことがおすすめです。
ここら辺、要望があれば別記事にて詳細を記したいと思っています。
選挙
選挙は当然ながら、住民票の置いてある地域の選挙区において投票する必要があります。
現在では、「不在者投票制度」があるので、バンライフで全国を旅していても投票することが可能ですね!
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。 また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。



バンライフしていても選挙は必ず行いましょう!
お金の問題
みなさんバンライフって、オフグリッドなライフスタイルだからお金かからないと思っていませんか?


確かに、
- 住居費用
- ガス代
- 電気代
- 水道代
などはかなり節約することが可能です。
しかし、上記でお伝えしたお風呂代やガソリン代、洗濯代などは家に住んでいる方よりも遥かに費用がかかります。
まずは「バンライフにかかる費用」を紹介しますので、参考にしていただき、どれぐらいお金をためておけばいいかを逆算してください。
まずは1人当たりかかるお金
- 食費:15000円(1日1500円)
- 風呂代:24000円(1日800円と計算)
- 洗濯代:4200円(5日に1回コインランドリー800円)
- 雑費:15000円(衣類・観光・宿泊)
- スマホ代金:2000円(LINEモバイルなど)
一人当たり5万円を超えます。
複数人でも変わらないお金
- ガソリン代:10000~30000円
- 高速代金:5000~30000円
- WiFi:4000円
- 車のローン:5000~50000円
- 車の保険代:5000~20000円
ここはみなさんそれぞれの金額だと思いますので、計算してみてください。
車のローンが完済しているのであれば、1人10万円以下でバンライフは可能だと思います。
逆に、車のローンを多く払っていたり、キャンピングカーなど大きな車に乗っている方で移動距離が長い人などは、20万ほどいくと思います。
しっかりと予想した上で、どれぐらい貯金をして、現状どれぐらい稼ぎがあるのかを見極めた上でバンライフの計画を進めていきましょう!
女子ならではの問題
バンライフをする若者が増える中で、女子1人でする人も当然ながらいると思います。
女子1人の場合、最大の問題点は「安全」ですね。
田舎の道の駅にはたくさんのキャンピングカーも泊まっていますし、結構、暗い場所も多くあります。
なので必ず、「防犯ブザー」「LEDライト」を持参し、トイレなどに行くようにしましょう!
また危険だなと思った場合はすぐさま、
- クルマを移動させる
- 夜中であろうが場所を移動する
などの行動に移しましょう!
虫対策
バンライフだけでなく、キャンプなどのアウトドアの際にも対策が必要な「虫」。


特に「蚊」は、危険な生物なので、しっかりと安全対策をとりましょう!
別記事にて、バンライフの「蚊」の対策と対策グッズ、そしてペットの蚊対策も記していますので、併せてご覧ください!


エコノミークラス症候群
エコノミークラス症候群とは、長時間同じ姿勢で座っていることで、血液の循環が悪くなり、血栓が起きる病気です。
バンライフでは、車内に長時間滞在することが多いため、エコノミークラス症候群のリスクが高くなります。
エコノミークラス症候群を予防するためには、以下の点に注意しましょう。
- こまめに立ち上がって体を動かす
- 水分をこまめに摂取する
- 足を組んだり、足を上げたりしないようにする
- 座席をリクライニングする
これらの点に注意することで、エコノミークラス症候群を予防することができるので、時折、思い出したらやってみましょう!!
まとめ
バンライフの全ての事例をもとに、記事を作成したのでかなり長くなってしまいましたがいかがでしたでしょうか?
バンライフは一見、若者の新しいチャレンジの場で、自由で楽しそうと思っていた方も多いかもしれませんが、「問題点」だらけなこともわかっていただけたと思います。
そしてバンライフは「電気代0円」「災害に強い」などのことから、非常にオフグリッドライフに似ています。
このメディアはオフグリッド専門メディアとして発信していて、なぜ「バンライフ」と思った方はこの記事を読んでなんとなく理解いただけたと思っています。
では最後に、この記事で紹介した別記事をまとめて紹介していていきます。