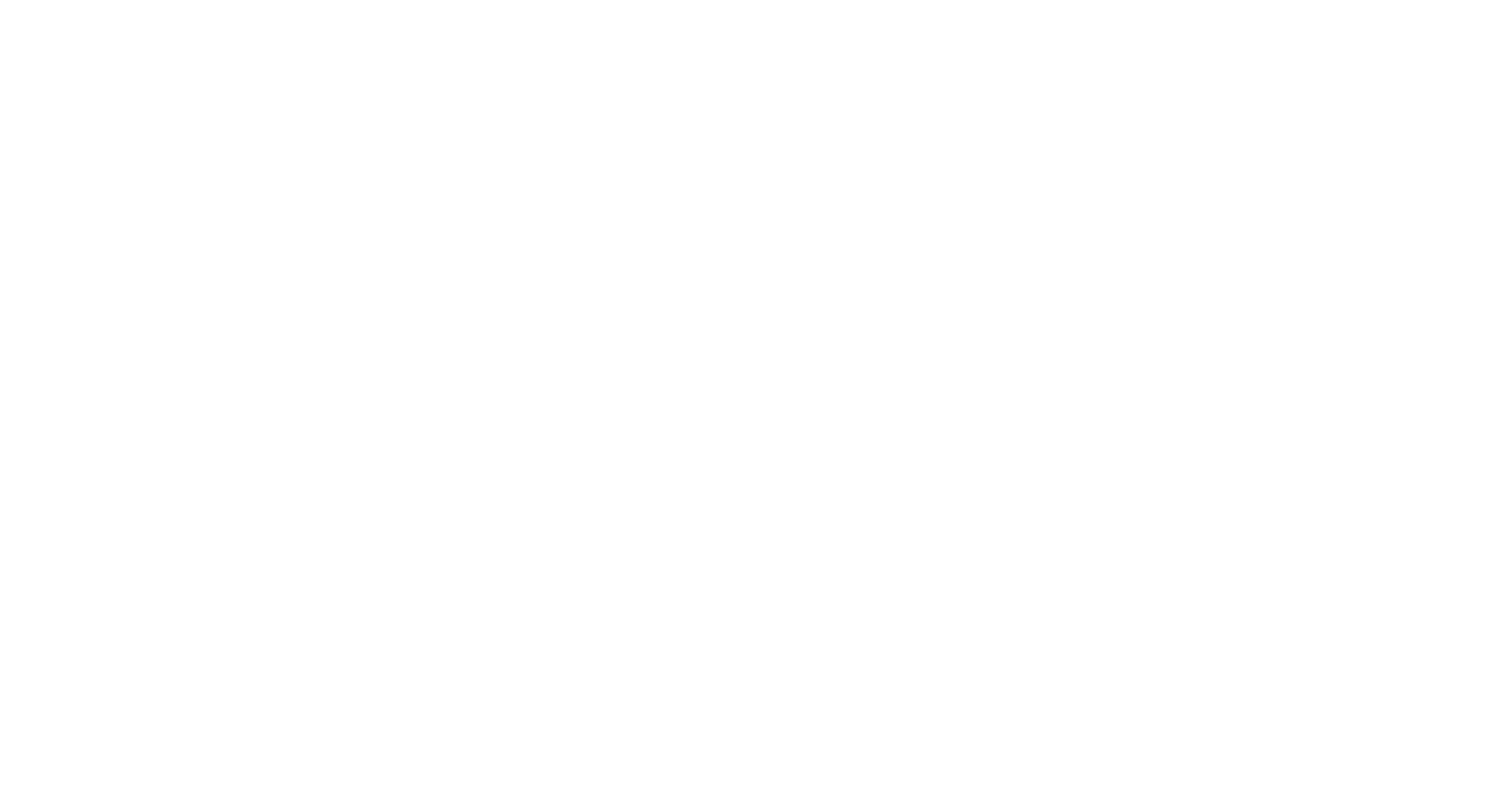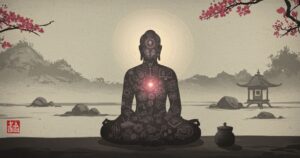東洋哲学を学び、マインドフルネスなYaiYu(@yusukeyaida)こと、矢井田裕左です。
本記事のテーマは「仏教」。その仏教の核心に「空(くう)」という概念が存在するのですが、非常に奥が深い。
この「空」の思想は、しばしば単なる「無」として誤解されがちですが、より深く探求することで、現代社会を生きる私たちが抱える様々な執着から解放され、「とらわれない暮らし方」を実現するための重要な鍵となることが見えてきます。
私も多く経験しているのですが、日々の生活の中で感じる様々なプレッシャーや期待は、時に私たちを不安や束縛感で満たし、自由を奪います。本稿では、仏教における「空」の基本的な意味を探り、それが特に私たちの感情とどのように関わり、「感情にとらわれない」生き方を実現する上でいかに役立つのかを考察します。
第一章:「空」の基本的な意味:固定された実体の否定

ちょっと難しいことから解説すると、仏教において「空」とは、あらゆる現象は固有の、不変の実体を持たないという真理を指し示します 。それは、すべての存在は様々な条件や関係性(縁起 – えんぎ)によって成り立っているという考えに基づいています 。
 YaiYu
YaiYuなんじゃそれって感じですよね。
もうちょっと噛み砕くと、この世界に存在するものは、単独で、そして永遠に変わらない本質を持っているわけではなく、常に変化し、他のものとの相互作用の中で存在しているという事、そのことを「空」を言うわけです。
冒頭でお伝えした、「空」は絶対的な「無」や「虚無」を意味するのではなく、変化しない、独立した自己や本質といった概念が存在しないことを示唆しています 。
最近読んだ面白い本に「しんめいP」著書の「自分とかないから〜教養としての東洋哲学」があるのですが、まさにこの「自分とかないから」が「空」を示唆していることがわかります。



難しい「空」の概念をとてもわかりやすく解説している本なので、かなりおすすめです!
ただ、私自身は上記の空の理解ができなかったので、もっと空の考え方を分かりやすくするために、身の回りにあるもので例えてみましょう。


例えば、私たちが普段使っている一枚の紙。パッと見ただけでは、ただの紙切れに見えますよね。でも、この紙がどうやってできたのかを考えると、たくさんのものが関わっていることが分かります。
- 太陽の光を浴びて育った木
- 木を切った人
- 雨が降って木を潤し
- 工場で働く人
- たくさんの機械やエネルギー
もし、これらのどれか一つでも欠けていたら、この紙は私たちの手元にはなかったかもしれません。つまり、紙というものは、それ自体が「これが紙だ!」と言えるような、変わらない本質を持っているわけではなく、色々な条件がたまたま組み合わさって、一時的に紙という形になっているだけなのです 。
そして、その紙も、何枚か集められて糊で綴じられれば、ノートという別の形に変わります。私たちはそこに様々な知識や感情を書き込みますが、使い終われば、そのノートは役目を終え、資源としてリサイクルされるか、あるいはただのゴミとして捨てられてしまうかもしれません。
同じ一枚の紙でも、その時々の条件や使い方によって、様々な役割や形に変化していくのです。このように、あらゆるものは固定されたものではなく、関係性の中で常に移り変わっていくというのが、「空」の基本的な考え方なのです 。
第二章:「とらわれない」とは:「空」がもたらす心の自由
このように、あらゆるものが不変ではなく、固有の本質を持たないという「空」の理解、なんとなく理解できたでしょうか?
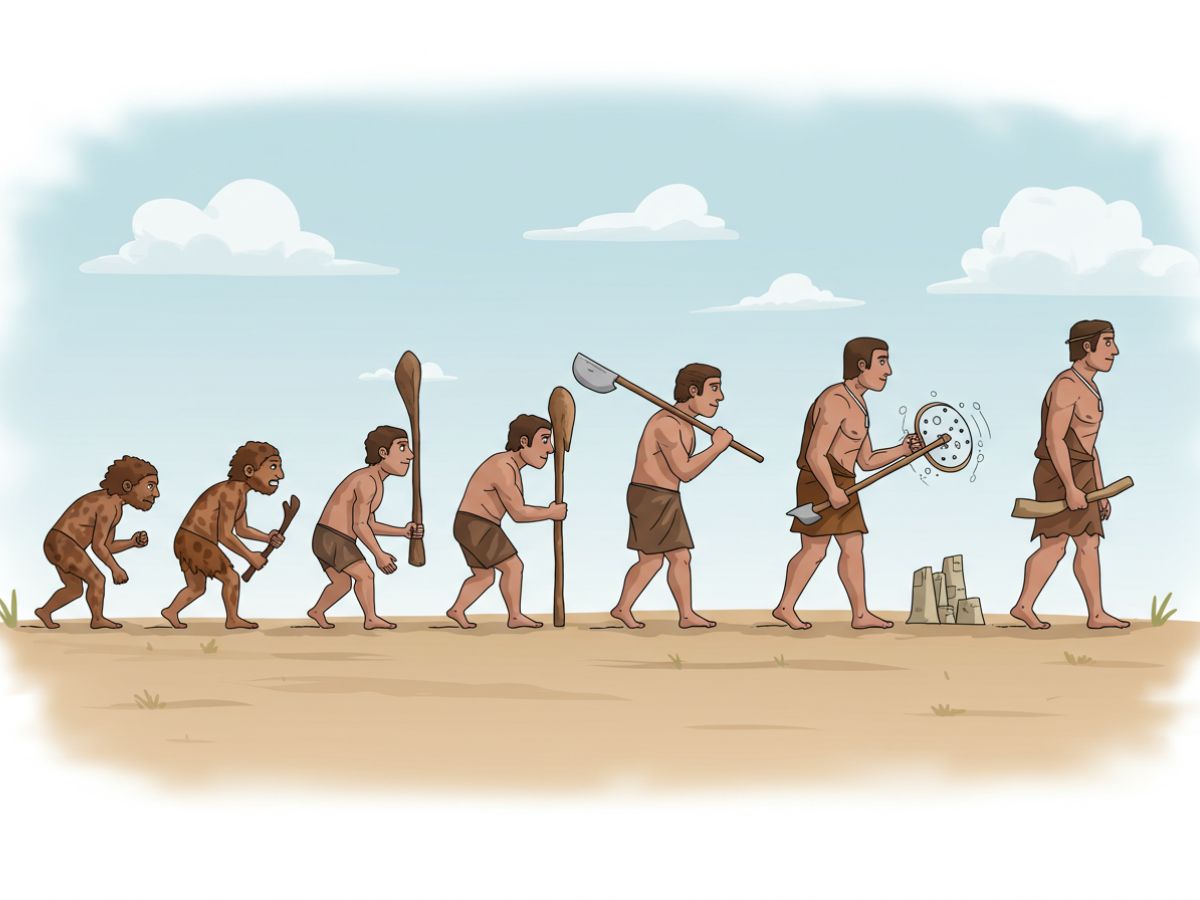
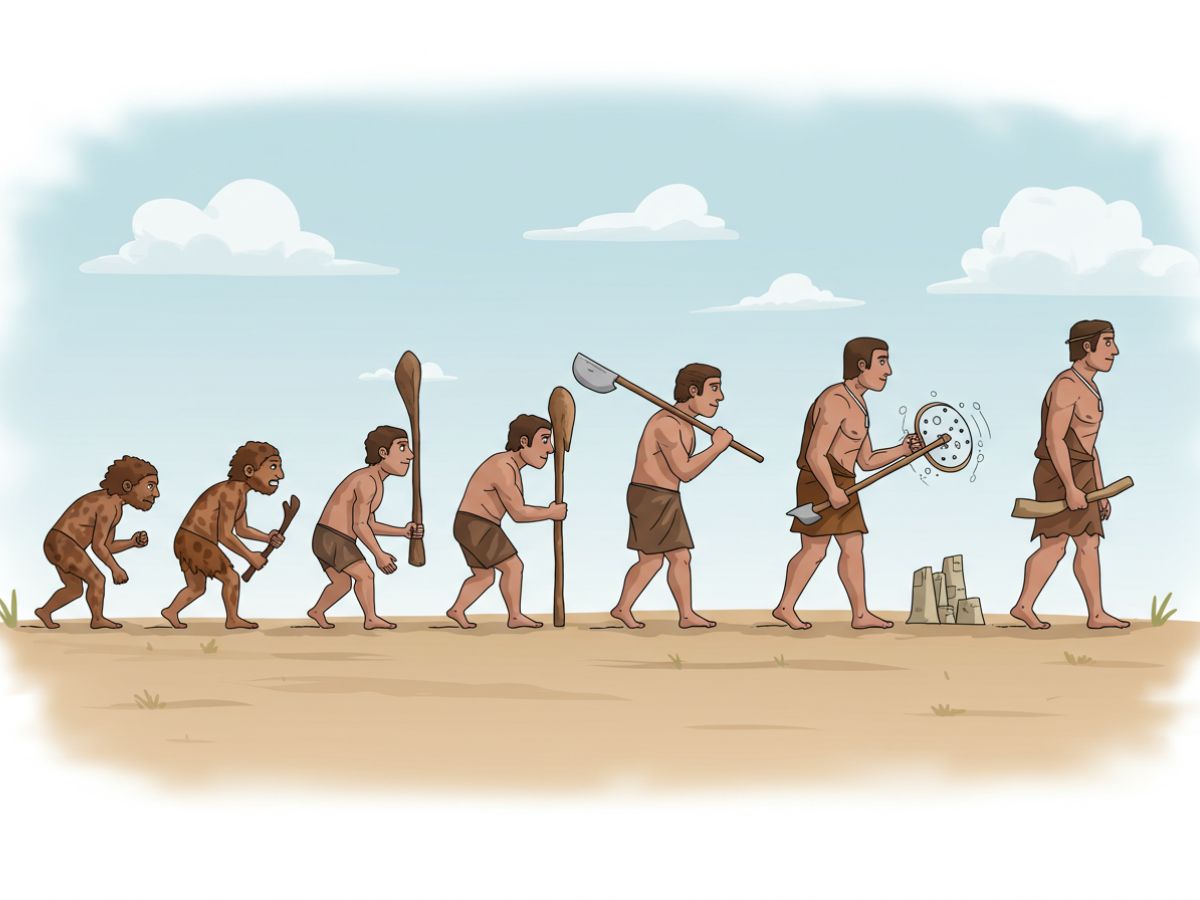
紙だけでなく、そんな私たち自身ですら、不変ではなく固有の本質は持っていないのです。
例えば、
- 髪の毛は毎日抜けるので、昨日と同じあなたではない
- 爪も伸びるので昨日と同じあなたではない
- 兄弟が生まれればあなたは兄(姉)になり弟(妹)になる
などなど。
さてここで本稿における「とらわれない」という生き方へと、この空は実は自然に繋がります 。
もし私たちが、常に変化し続けるものや、本質的に独立して存在しないものに執着してしまうと、それらが変化したり失われたりする際に、苦しみを感じることになります 。例えば、美しい花に心を奪われ、その美しさが永遠に続くことを願ったとしても、花は必ず枯れてしまい、その時、私たちは失われた美しさへの執着から、悲しみや喪失を感じるでしょう。
しかし、「空」の理を理解することで、私たちはこれらの移ろいゆくものへの執着を手放し、心の自由と安らぎを得ることができ、執着から解放されることで、私たちは現在この瞬間の経験をより深く味わうことができるようになります。
薬師寺の高田好胤師は、「空」の心を「かたよらない心。こだわらない心。とらわれない心。広く広く、もっと広く。これ般若心経、空の心なり。」と表現しています 。
「とらわれない」とは、感情を抑圧したり、世俗から離れて生きるということではありません。
本メディアでもテーマにしている、
- オフグリッド生活:世の中のインフラに依存しない生活
- 自給自足生活:主に食料を自分たちで生産し生きる生活
- ノマド:オフィスや家を持たない生活や働き方のこと
これらも、世俗から離れて生きるということではなく、変化し続ける現実を受け入れ、何かに固執することなく、柔軟に対応していく心のあり方が生活に現れていることを示唆しています。
それは、自分の感情や思考、人間関係、物質的なものなど、あらゆるものに対して、絶対的な所有感や永続性を求めない生き方と私は考えています。



私は、オフグリッド生活やノマドだったので、この空をなんとなく実践していたのかも知れません。
第三章:「感情」と「空」:心の動きに囚われない生き方


第二章では空を「もの」で例えて表現しましたが、私たちの心の中で生じる様々な「感情」もまた、空の性質を持っています 。
- 喜び
- 悲しみ
- 怒り
- 楽しみ
これら感情は、それぞれ様々な原因や条件(縁起)によって生じ、そして変化し、消え去っていくもので、それらの感情は「固定された独立した実体」を持っているわけではありません。



空のイメージを、ちょっとくどいですが、何度も説明しています!
私たちが感情に執着すると、苦しみが生じます 。
例えば、喜びの感情に固執すれば、その喜びが過ぎ去った時に喪失感を覚え、怒りの感情に囚われれば、その怒りが自分自身や他人を傷つけることがあります。感情は常に移ろいゆくものなのに、私たちはそれを永遠に保持しようとしたり、あるいは避けようとしたりするために、苦しみを増幅させてしまうのです。
空の概念で感情も考えてみると「感情には固定的な実体がない」ということになりますよね?
そう認識することで、私たちは感情に対して一歩引いて観察する余裕を持つことができ、まるで空に浮かぶ雲のように、感情は現れては消えていく一時的な現象であると捉えることができるのです 。



ちょっとまだ抽象的なので具体的に解説。
日常生活において、感情の「空」を理解し、実践する例を考えてみましょう。
例えば、仕事でミスをして強い怒りを感じた時、私たちはその怒りの感情で、「自分はなんてダメなんだ」と自己嫌悪に陥ったり、相手を責めたりすることがあります。
この時、心臓がドキドキしたり、顔が熱くなったり、頭の中で「なぜこんなミスをしたんだ」「あの人のせいだ」といった考えが何度も駆け巡ることがありませんか?
しかし、「空」の視点を持てば、まずその怒りの感情を俯瞰し「今、自分は怒りを感じている」と認識し、体のどこが熱くなっているか、どんな思考が頭の中を駆け巡っているか、といった感覚や思考をただ観察するのです。
まるで、空に浮かぶ雲を眺めるように、湧き上がってくる感情をただ見つめます 。そのように観察することで、怒りの感情は単なる一時的なエネルギーの動きであり、固定された「自分」そのものではないことに気づくことができます。感情に囚われず、その本質を見抜くことで、私たちはより冷静に対処し、建設的な行動をとることができるようになります。
別の例を挙げましょう。
楽しみにしていた旅行が急にキャンセルになって、強い悲しみを感じたとします。その瞬間、「もう何もかも嫌だ」「なんで私だけこんな目に遭うんだ」といったネガティブな感情に支配されるかもしれません。
しかし、「空」の視点から見れば、この悲しみもまた、様々な条件が重なって生じた一時的な心の動きに過ぎません。時間が経てば、この悲しみは薄れていく可能性が高いですし、新たな楽しい出来事が現れるかもしれません。悲しみにしがみついていると、その苦しみは長引きますが、悲しみの「空」を理解し、ただ感じていれば、やがてそれは過ぎ去っていくのです。
喜びの感情も同様です。宝くじに当たって大喜びしたとしても、その喜びは永遠に続くものではありません。時間が経てば日常に戻り、喜びの感覚も薄れていくでしょう。喜びの感情に執着しすぎると、それがなくなった時に大きな喪失感を感じてしまうことがあります。
感情は常に変化していくものだと理解することが、「とらわれない」生き方への第一歩となるのです。
第四章:仏教各宗派における「空」の解釈:多様性と共通点
この章はちょっと座学になります。


仏教における「空」の解釈は、宗派によって多様な側面を持っていて分類しているのですが、苦からの解放という根本的な目的においては共通しています 。
| 宗派 | 「空」の主な解釈 | 関連する概念 | 関連する経典 |
| 上座部仏教 | 五蘊における「無我」(固定された自己の欠如) | 無我 , 五蘊 ,縁起 | 各阿含経, スッタニパータ |
| 大乗仏教 (Mahayana) | 全ての現象における「空」(固有の存在の欠如) | 法空, 縁起, 二諦説 | 般若経 , 般若心経 , 中論 |
| 禅宗 (Zen) | 「無」の直接体験(言葉や概念を超えた空の体感) | 無, 自他不二, 坐禅 | 特になし |
初期仏教(上座部仏教)においては、「空」は主に自己の空、つまり五蘊(色、受、想、行、識)の中に固定された、不変の自己が存在しないという意味で理解されます 。これは、自己への執着が苦の根源であるという考えに基づいています。



最近の若者の「何者かになりたい」も、私は自己への執着だと考えています。
このテーマでも面白い本を紹介。目から鱗満載です。
さて大乗仏教になると、「空」の概念はさらに広がり、自己だけでなく、あらゆる現象もまた固有の存在を持たないと説かれるようになります 。この思想を代表するのが「般若経」であり、そのエッセンスを凝縮した般若心経は、「色即是空、空即是色」という有名な言葉で、「空」の深遠な智慧を伝えています 。
禅宗では、言葉や理屈による理解だけでなく、坐禅などの実践を通して「無」や「空」を直接体験することを重視します 。坐禅を通じて自己と他者、世界との境界線が曖昧になるような体験は、「空」の入り口となると言われています 。
このように、宗派によって「空」の解釈には細かな違いがありますが、いずれの教えも、固定された実体への執着から離れ、真の自由(解脱)を得るための重要な概念として「空」を位置づけているのです 。
第五章:「空」の思想を現代に活かす:感情との向き合い方
「空」の思想は、感情の本質を理解する上で重要な視点を与えてくれますが、頭で理解しただけでは、どうしても感情に囚われてしまうのが人間というものです。


ここでは、「空」の理解を深めながら、湧き上がる感情にどのように向き合い、コントロールしていくか、そしてコントロールが難しい場合の対処法について、より具体的に解説します。
感情の観察とマインドフルネス
感情に圧倒されそうになった時、まず試してほしいのが、その感情を客観的に観察することです 。怒り、悲しみ、不安など、どんな感情であっても、良い悪いと判断せずに、ただ「今、自分は〇〇と感じている」と心の中で言葉にしてみましょう。そして、その感情が体のどこに現れているか(例えば、胸の締め付け、喉のつまり、手の震えなど)、どのような思考を伴っているかを観察します。これは、マインドフルネス瞑想の実践そのものです 。
感情は、空に浮かぶ雲のように、常に変化し、やがて消え去るものです 。感情に気づき、観察することで、私たちは感情と一体化することなく、一歩引いて見守ることができます。感情に「実体がない」という「空」の理解を深めることで、感情に振り回されることなく、冷静さを保つことができるようになります 。
コントロールを手放す
感情をコントロールしようとすればするほど、かえって苦しくなることがあります 。
特に強い感情は、無理に抑え込もうとすると、心の中で反発したり、別の形で現れたりすることがあります。仏教では、感情を無理にコントロールするのではなく、その感情をありのままに受け入れることも大切だと考えます。感情が湧き上がってきたら、「ああ、今私はこの感情を感じているんだな」とただ認識し、その感情が過ぎ去るのを待ちます。
瞑想の実践
日々の瞑想は、感情の観察力を高め、「空」の理解を深める上で非常に有効な手段です 。瞑想を通して、私たちは思考や感情の流れを静かに見つめる訓練をします。 瞑想は、感情が湧き上がっても、それにすぐに反応するのではなく、一時的な現象として受け流す力を養います。
コントロールできない時の対処法
どうしても感情に囚われてしまい、コントロールできないと感じる時もあるでしょう。そのような場合は、以下の対処法を試してみてください。
- 呼吸に意識を向ける: 深くゆっくりとした呼吸を繰り返すことで、心身を落ち着かせることができます 。
- 場所を変える: 感情が強く湧き上がる場所から一時的に離れることで、気分転換になり、冷静さを取り戻せる場合があります。
- 体を動かす: 軽い運動やストレッチをすることで、心身の緊張を和らげ、感情を解放する助けになります。
- 慈悲の瞑想: 他の人の幸福を願う慈悲の瞑想は、怒りや憎しみといったネガティブな感情を和らげる効果があると言われています 。
- 信頼できる人に話す: 誰かに話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。
感情に良い悪いはない
仏教の「空」の考え方に基づけば、感情そのものに良いも悪いもありません。喜びも悲しみも、怒りも楽しみも、すべては一時的な心の動きであり、固定された実体を持たないものです。私たちが苦しむのは、感情に執着し、それを永遠に保持しようとしたり、避けようとしたりするからです。感情の「空」を理解し、感情との適切な距離感を保つことで、私たちはより穏やかに、そして自由な心で生きていくことができるでしょう。
結論:「空」を通して見つける、真の自由と安らぎ
仏教における「空」、少しはその概念の素晴らしさに気づいていただけたでしょうか?
空はあらゆる存在は固有の、不変の実体を持たないという理解であり、それは私たちの感情を含むすべての現象に当てはまり、この「空」の思想を深く理解することは、感情への執着から解放され、「とらわれない暮らし方」を送るための重要な道標となります。
感情を客観的に観察し、その一時的な性質を認識することで、私たちは感情に振り回されることなく、心の自由と安らぎを得ることができます。
マインドフルネスや瞑想などの実践を通して「空」の理解を深めることで、私たちは変化し続ける人生の波の中で、より穏やかに、そして柔軟に生きることができるようになり、固定された考え方や感情に囚われることなく、あらゆる可能性を受け入れ、今この瞬間を大切に生きる。
それこそが、「空」の思想が私たちにもたらす、真の自由と安らぎに満ちた生き方なのです。